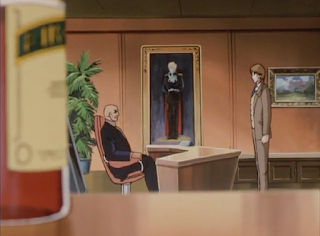帝国軍によるイゼルローン要塞の奪還を確実にするため、
・イゼルローン要塞からヤン・ウェンリーを引き離す
・ガイエスブルク要塞を移動要塞化しイゼルローン回廊に大軍を送り込む
という二つの策謀が同時並行で進んでいる頃、帝国軍の双璧、オスカー・フォン・ロイエンタールとウォルフガング・ミッターマイヤーの両提督は、食後の談笑をしていました。
その中で話題に上がったのは、4年前に彼らが初めてローエングラム侯爵ラインハルト(当時は旧姓を名乗っていたため、ラインハルト・フォン・ミューゼル)をその目で見た時の印象でした。彼らの会話は、以下のとおりです。
ミッターマイヤー「どう思う、金髪の小僧とやらを」
ロイエンタール「昔から言うだろう、虎の子を、猫と見誤ることなかれ、と」
ミッターマイヤー「ラインハルト・ミューゼルは、卿の見たところ、虎か、猫か」
ロイエンタール「多分、虎の方だろう。姉が皇帝陛下のご寵愛を受けているとはいえ、敵のやつらがそんなことに遠慮する理由はないからな」
ここで学んだのは、偏見を捨てて客観的に事実を見ることが大事、ということでした。
当時、門閥貴族達の間で、ラインハルト・フォン・ミューゼルの評判は芳しくなく、「金髪の小僧」「姉のスカートの中に隠れている」と揶揄されていました。その評判は、実際に彼が陣頭に立っていくつかの戦いで勝利した後でも、大して変わりませんでした。
他方で、ロイエンタールの見解は適切で、ラインハルトという個人を見る際に、「姉が皇帝の寵姫である」、「飛びぬけて若い(当時はまだ十代)」、「顔が綺麗」といった観点を全て捨てて、ただ「戦いが強いかどうか」という点(つまり、成果)を見ています。また、その成果の測り方も、上官の評価やマスコミの評判などではなく、敵側の視点を用いたものでした。
この一見簡単なことが、現実世界ではなかなか難しいのだと思います。私が中学時代に小説を最初に読んだときは、「門閥貴族達は見る目がない」と、むしろ彼らに人を見る能力がないように思ったものでした。しかし、実際に自分が社会人になって人を見極める側に回った際には、どうしても学歴や風貌といった実績面以外に目が行ってしまいます。このあたり、言うは易く行うは難しの典型だと思います。
この偏見を避けるためには、実際に自分の目で確かめる、例えばビジネスの場合は短期間でも一緒に仕事をしてみる、といった方策が有効だと思います。実際、ファーレンハイトやメルカッツ、ミュッケンベルガーといった面々は、ラインハルトの仕事ぶり・有能ぶりを共に戦い肌で感じることで、偏見にとらわれることなく彼を評価することができるようになりました。(そういう意味では、一度も一緒に仕事をすることなく、ラインハルトを正しく評価できたロイエンタールの慧眼は恐ろしいの一言です)。
さて、ここでのもう一つの学びは、強すぎる光に惑わされない、という点です。
当時、ラインハルトの傍には、いつもキルヒアイスがいました。そして、目立つのは常にラインハルトであり、キルヒアイスは影のような存在で特に誰にも意識されていませんでした。(キルヒアイスに「個人的に」ご執心のヴェストパーレ男爵夫人は例外ですが)。
しかし、キルヒアイスの能力や人望、特に上級大将に昇進してからの彼の活躍は、ラインハルトに勝るとも劣らない素晴らしいものでした。このシーンの続きでロイエンタールが「キルヒアイスの力があれほどとは、さすがに気づかなかった」と述べている通りです。キルヒアイス本人は特に気にしていなかったはずですが、(無視されるという)不当な評価を受けていたと言えます。
どこの世界にも、ラインハルトのような目立つ存在、キルヒアイスのように影に隠れる存在、どちらも居ると思います。そして、目立つから有能、影だから無能、ということではなく、むしろキルヒアイスのような影の存在がラインハルトという光をより輝かせている可能性について、常に意識すべきだと思っています。